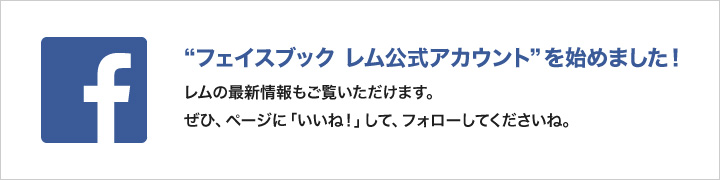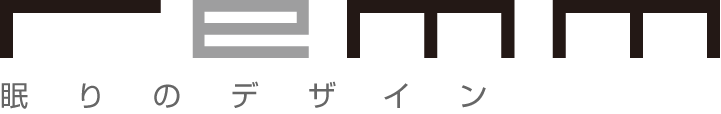
MAIL MAGAZINE Vol.4 2018

知られざる都会のオアシスの意外な歴史
JR御茶ノ水駅の聖橋口を出て、Uターンするように左折すると、関東大震災復興の願いを込めて架けられた聖橋がある。橋の上から右手に見ると、神田川を中心に総武線と中央線、丸ノ内線がハの字を描くように姿を現す。この鉄道ファン屈指の撮影スポットの脇、聖橋を渡ったところにあるのが史跡・湯島聖堂だ。
湯島聖堂に来て感じるのは、鉄道3路線の脇にありながら、驚くほど静かで厳かな雰囲気が漂っていることだ。都会の喧騒を忘れられる場所であり、近所にある神田明神との賑わいの差に驚く。
聖堂の歴史は、徳川五代将軍・綱吉の時代にさかのぼる。元禄3年(1690年)、綱吉は儒学の振興を図るため、幕府の学問を司った林家の塾を上野・忍岡からこの地に移した。寛政9年(1797年)には、幕府直轄学校である昌平坂学問所が開設。学問所は維新後の明治4年(1871年)、惜しまれながら75年にも及ぶ歴史を閉じた。
しかし、学問所の幕を下ろすも、勉学拠点としての歴史は続く。敷地内には、同じ明治4年に文部省、後に上野に移転する東京国立博物館が、翌5年(1872年)には筑波大学の前身である東京師範学校、後のお茶の水女子大学にあたる東京女子師範学校が設置された。それぞれの規模が大きくなるにつれ、この地から移転した。
大正11年(1922年)、聖堂は国の史跡に指定される。だが翌12年(1923年)に関東大震災が起こり、広い敷地にもかかわらず、入徳門と水屋だけを残し、すべてを焼失してしまう。哀しい歴史があったからこそ、脇に架かる聖橋は関東大震災の復興の願いが込められているのだ。
現在の湯島聖堂は、昭和10年(1935年)に再建したもの。震災で焼け残った入徳門以外は、耐震耐火のため鉄筋コンクリート造りとした。目を引くのは、やはり間口20メートルの大成殿だろう。大成とは、孔子廟の正殿のこと。総黒漆塗りのシックな佇まいの中に、中央に孔子像、左右に孟子・顔子・曽子・子思の四賢人が祀られている。
受験シーズンには、大成殿前にたくさんの合格祈願の絵馬が掛けられていた。皆、希望の学校には入学できただろうか。
ライター/横山由希路