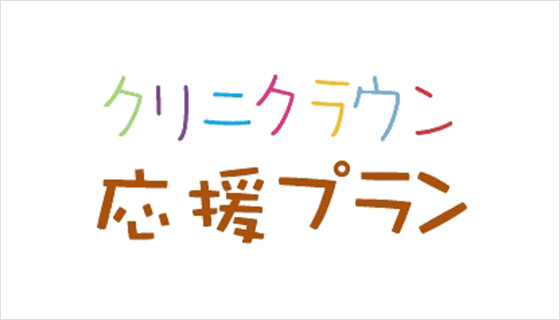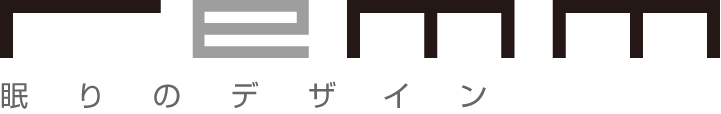
MAIL MAGAZINE Vol.4 2022

有名企業の社史を、1人の美術家がアートと
世相分析を絡めて紐解く。
編集の妙を体験できる展覧会
やだぁ~、すっごく面白い。小さいギャラリーなのに、来場者はそこかしこで写真を撮りまくる。都合1時間は会場にいただろうか。その会場は、資生堂ギャラリー。あの赤茶色の建物が映える東京銀座資生堂ビルの地下1階にある。
注目の展示は、5月29日(日)まで開催の「万物資生|中村祐太は、資生堂と を調合する」。文献調査をもとにした作品で知られる美術家の中村祐太が、創業150年の資生堂の社史を縦軸に、大正から昭和初期まで活躍した今和次郎の風俗分析と、美術家・赤瀬川原平の視点を横軸として織りなした展覧会だ。「編集する」と表現せずに「調合する」と冠するのが面白い。そう、資生堂の事業は洋風調剤薬局からスタートしているからだ。
驚いたのは企業としての先見の明。1902(明治35)年にはソーダ水やアイスクリームを製造販売し、1915(大正4)年には初代社長の福原信三が「花椿マーク」を考案していた。また昭和初期の段階で、絵本や子ども服など、様々な事業にも挑戦。主力の化粧品、パーラーだけでなく、あらゆる分野で「粋で繊細でカッコよく」を目指していたことがわかる。
これら資生堂の社史に関わる革新的な内容を、今和次郎や岸田劉生らのエッセイ、資料と共に理解するのが本展のポイントだ。当時の人々の関心や風俗がわかるため、来場者は生まれる前の内容なのに、時代背景を理解しながら「銀ブラ」しているような気になれるのだ。
また時代を作っていた人々の気概を、そこかしこに感じる。例えば1923(大正12)年の「バラック装飾社 案内状」には、関東大震災で廃墟と化した東京を眺めて、こう記している。「バラック時代の東京、それが私達の芸術の試験を受けるいい機会だと信じます」。事業を再開するのに、掘っ立て小屋から始めないというのだ。バラック建築でもカッコいい店構えで始めようと呼びかけている。写真でも、競うように粋なバラックを建てていた様が垣間見られる。
本展は資生堂企業資料館でしか見られない貴重な展示も多い。「花椿マーク」の由来となった「香水 花椿」の小瓶、昭和初期の資生堂パーラー「卓上メニュー」の現物。しゃがみ込んだり、覗き込んだりしながらご覧あれ。結構時間がかかります。
ライター/横山由希路