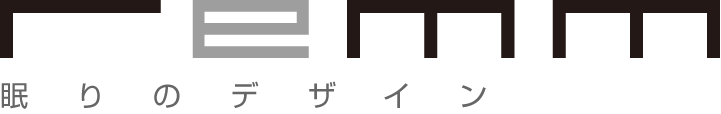
MAIL MAGAZINE Vol.5 2022

写真も名画もたちどころに理解できる。
キュレーションがピカイチの展覧会
いつも美術館に行くたびに感じていることがある。もっと作品を深く理解できたらと思う。
背景や制作意図を手がかりに、自分の側から作品にアプローチする。なんとなくわかった気になって次の作品に歩を進める。もしも作品の側から理解されたがっている体で、鑑賞者である私に近づいてきたら? 実はそれをキュレーションで可能にしている展覧会を見つけた。それが「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×柴田敏雄×鈴木理策 写真と絵画-セザンヌより 柴田敏雄と鈴木理策」。東京駅にほど近いアーティゾン美術館で、7月10日(日)まで開催中だ。
この展覧会は、写真を表現媒体として選んだ2人の作家が、セザンヌやモネ、アンリ・マティスらの作品を起点に写真と絵画の関係性を問うたもの。面白いのは展示の順番だ。自然の中の人工的な構造物を題材にしてきた柴田敏雄のゾーンでは、土砂崩れ防止用に作られたコンクリート製の砂防堰堤や稲刈り後の田んぼといった柴田の写真の後に、その構図や手法に共通点のあるマティスやピート・モンドリアンの作品が飾られる。またカメラの知覚を通して、人がものを観ることへの問題意識を問いかける鈴木理策のセクションでは、水辺を撮った鈴木の作品とモネの「睡蓮」「睡蓮の池」などが交互に展示されている。
なんというか、よく練られた学習ドリルのようで、順番に観るだけで写真にも絵画にも深くアプローチできるのだ。名画は実際の情景の何を誇張して、何を簡略化しているのか。写真家はカメラの技術を使って、名画のように何を際立たせ、何を単純化しているのか。また鈴木のパートでは、カメラは人間の目のように「観たいものだけを観る」ものであることがわかる。画角の多くにピントを合わせたつもりでも必ず曖昧な部分が存在し、人の目とカメラの関係性についても考えさせられる。
写真が普及し始めたのは19世紀後半。当初から絵画的な表現が模索された写真と絵画は、ともに影響を及ぼし合いながら発展していった。翻って、現代の私たちのカメラ表現はどうだろう。もはや記録と映えばかりではないか。柴田や鈴木の写真をスマホのカメラに収めながら、美術館でそんなことを感じた。
ライター/横山由希路






