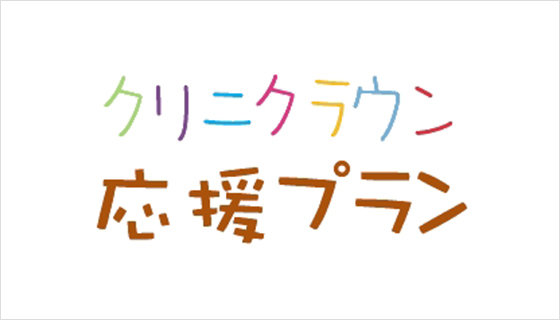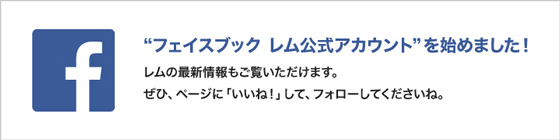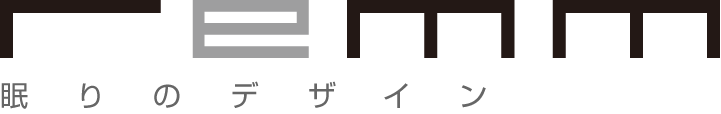
MAIL MAGAZINE Vol.6 2022

まるで自宅が美術館。
住友家の御曹司のコレクションで日本の絵画史を学ぶ
平日木曜の昼下がり、その場所に赴くと意外にも来場者が数多くいた。都心の穴場ともいうべき小さな美術館なのに。そこは「泉屋博古館東京」。地下鉄六本木一丁目駅直結の泉ガーデンの敷地内にある。
2002年から旧住友家麻布別邸跡地に「泉屋博古館分館」の名で長らく親しまれたこの美術館は、2022年3月に名称も新たにオープンした。現在は、リニューアルオープン記念展の第2弾が7月31日(日)まで開催中。展覧会のタイトルは「光陰礼讃―モネからはじまる住友洋画コレクション」だ。
住友洋画コレクションとは、明治・大正時代に住友グループの基礎を築いた住友家15代当主・春翠が収集したもの。彼のコレクションは、明治30(1897)年にパリで印象派のモネの油彩画2点を入手したことから始まった。当時のフランス画壇は印象派の台頭で古典的写実派が衰退していたものの、春翠はジャン=ポール・ローランスなどの古典派絵画もバランスよく収集した。
光を追い求めた印象派と陰影表現を追究した古典派。この2つを「光陰」と捉え、そこから発展した日本近代洋画を紹介したのが今回の展示だ。
例えばモネの「モンソー公園」。この絵画はやや雲がかった日差しの中で、木々を通していろんな表情の光が公園の遊歩道を照らしている。この光の表現は、やがて窓辺で読書する女性を描いた藤島武二の「幸ある朝」などに影響を与えていく。一方、ジャン=ポール・ローランスの「マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち」は、注目させたい人物にスポットライト風の陰影をつける。この描写は「ノルマンディーの浜」の作者・鹿子木孟郎などに影響を及ぼしていく。その他「読書の後」で知られる山下新太郎は、“北野ブルー”でおなじみの北野武監督作品にも似た外光表現で目を引いた。
ちなみに本展の最後は種明かしがある。展示中の国内外の洋画が明治時代、住友春翠が建てた洋館のどの部屋に飾られていたのかが明かされている。彼が神戸の須磨海岸に築いた洋館はさながら美術館だった。そして日本近代洋画の絵画史そのものだった。キュレーターが付けたであろう絵画ごとのキャッチコピーを見ながら鑑賞すれば、自ずと日本の洋画史が頭に入るはずだ。
ライター/横山由希路