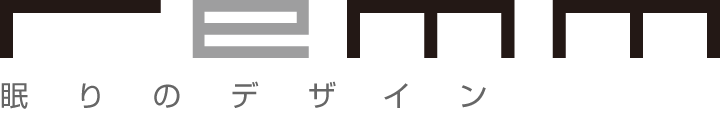
MAIL MAGAZINE Vol.7 2022

圧倒的な「朝ドラ」感とひとり「電通」感。
あっぱれな企業ミュージアム「江崎記念館」
JR神戸線、大阪駅の隣の塚本駅。そこから歩く。15分歩く。見えてくるのは、江崎グリコの工場。敷地内にある真っ白な建物が「江崎記念館」だ。コロナ禍で見学は電話での予約制で、案内には必ず社員がつく。本来1時間見学のはずが、私だけ2時間コースという贅沢。後ろの予約が入っていなかったらしい。
この記念館は社員に自社の歴史を知ってほしいとのことで、創業者・江崎利一の発案で建てられた。その後、関係先の企業からも注目を浴び、一般公開される。私は「グリコのおまけの展示数が尋常じゃない」との触れ込みでやって来たが、江崎利一の人生ドラマがおまけのインパクトを凌駕していた。
江崎利一の佐賀の実家は薬屋だ。父が亡くなると遺されたのは膨大な借金。当時流行っていたぶどう酒に目をつけ、その販売業で父の借金を返し、大阪進出の資金も貯めた。ぶどう酒業の販路を広げるため、いち早く買った米国製の自転車で、ある日利一は有明海沿いの牡蠣小屋のそばを通る。薬剤の知識のあった彼は牡蠣の煮汁を捨てる様を見て、「煮汁にグリコーゲンが入っているに違いない」と煮汁を分けてもらい、その足で九州大学に成分分析を依頼する。見立ての通り、牡蠣の煮汁にグリコーゲンが入っていた。そこからグリコーゲン入りの食べ物を作る「グリコ」が始まった。
ここまでの話が明治~大正初期。その後、グリコマークやグリコを含むデザイン・社名の原案を地元佐賀の小学生相手に複数見せ、マーケティング手法を大正時代に確立する。大阪で知られる存在になった「グリコ」は、昭和8年頃に東京進出。店は作らず、無人販売機を量産した。お金を入れると人気歌舞伎俳優の出演するトーキーが見られる仕掛けで、映画宣伝にも一役買っており、それら販売機を銀行に置くなどして人々の度肝を抜いた。
薬剤に長けた食品研究家で、作った品は知られてナンボ、人を驚かせてナンボのド級のアイデアマン。販促、宣伝、販路拡大。見学途中で「もう、ひとり『電通』感、すごいな」って感想が溢れ出てしまう。その江崎利一の名言はいくつかあるが、これにはシビレた。「アンタ、口がクサくなるまで考えたか?」。頼む、誰か早く朝ドラにして!
ライター/横山由希路






