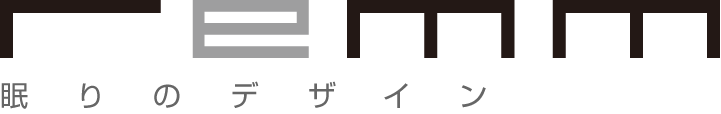
MAIL MAGAZINE Vol.2 2023

あの大人気漫画の基となる映像も。
国立映画専門機関で希少な映像を愉しむ
開催中の企画展を観に行ったはずが、すっかり常設展に目を奪われてしまった。それが東京・京橋の国立映画アーカイブ。ベテランの映画ファンは、旧東京国立近代美術館フィルムセンターと言った方がピンと来るだろうか。2018年4月に東京国立近代美術館より独立し、建物はそのままに、名称を東京国立近代美術館フィルムセンターから新たにした日本で唯一の国立映画専門機関だ。
常設展のタイトルは、『NFAJコレクションでみる 日本映画の歴史』。「日本映画のはじまり 映画前史~910年代」から「日本映画のひろがり 1960年代以降」「日本のアニメーション映画」まで、7章仕立ての構成で魅せる。
驚いたのは、ド頭で展開されている『明治の日本』と題された22分間のシネマトグラフだ。これは1897~99(明治30~32)年に、フランスの映画技師フランソワ=コンスタン・ジレルとガブリエル・ヴェールが撮影した記録映像。なかでもジレルが撮った『蝦夷のアイヌⅠ・Ⅱ』は、生活に密着したアイヌの古式舞踊が活き活きと映し出されている。漫画『ゴールデンカムイ』の読者なら、もうお気づきだろう。漫画やアニメ版にある『シネマトグラフ』の回の基となった映像がこれだ。当時のフィルムは燃えやすいためにその多くが失われたものの、『蝦夷のアイヌⅠ・Ⅱ』は2本合わせて3分ほどの映像とはいえ、他の作品に比べて鮮明で状態もよい。作者の野田サトルも史実やシネマトグラフに忠実に作画していることがわかり、金カムファンには嬉しいコーナーだ。
歌舞伎ファンのお宝映像もある。1899(明治32)年の歌舞伎舞踊『紅葉狩』は、日本人が撮影した最古の映像だ。やや早回し気味で再生されるものの、名優・九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎の巧みな舞いに思わず大興奮してしまった。そのほか、多重露出や素早いモンタージュの連打で精神病女性の内面を描いた衣笠貞之助監督の『狂った一頁』は、1926(大正15)年の作品ながら、1960年代の映画にも通ずるアバンギャルドな内容だ。
日本の映画界を支えた好奇心と執念と勢いを堪能しに来てほしい。帰り際、iPhoneで街中を動画撮影しながら、国立映画アーカイブでの映像の重みと自分が撮る動画の軽さに驚いた。
ライター/横山由希路






