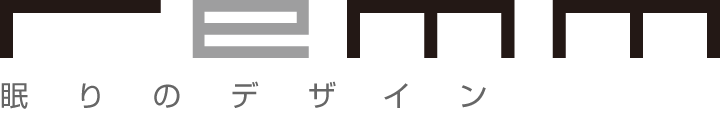
MAIL MAGAZINE Vol.10 2023

政治家、官僚から町の市民まで。
復興への思いがほとばしる関東大震災展
今から100年前、東京の日比谷公園は憩いの場所から市民の仮設住宅地へと姿を変えた。たくましい市民は崩れた旧音楽堂の屋根に布団を干し、飲食業者はライスカレーの屋台を出した。
関東大震災から100年を経た今、園内の日比谷図書文化館では、11月26日(日)まで貴重な展覧会が開催されている。それが特別展「首都東京の復興ものがたり-未来へ繋ぐ100年の記憶-」だ。
本展の見どころは、「建造物」に焦点を当てたこと。初公開の資料や豊富な写真・映像とともに、震災前後の東京の姿や復興の歩みを紹介する。地震発生から3日間、火災が続いた東京は焦土と化した。都市の不燃化や耐震化といった重い課題に向き合ったのは、為政者や建築家ばかりでない。市民の協力があってこそだった。
復興院総裁となった内務大臣の後藤新平は、震災翌日から燃え広がらない街を目指して、「焼失地域における土地区画整理」と「建物の鉄筋コンクリート化」に着手した。
会場では、震災前の区画図の上に拡張した主要幹線道路の予定図が黒く塗り重ねられ、市民がどのように引っ越したのか、映像で移転の様子を映し出していた。面白かったのは、新区画に家ごと引っ越す人々の様子だ。ジャッキで木造家屋の下から持ち上げ、宙に浮かせたまま、建物ごと移動させる。また自宅が焼失した人たちは、代替地に新しい番地が採番され、住まいができると次々と越していった。
区画整理で市民が住む場所を移せば、当然公共施設も移転を余儀なくされる。驚いたのは大正15年に出された「和泉小学校移転反対陳述書」だ。移転予定地の住民がNOを突きつけていたのだ。その一方で、「復興小学校」と呼ばれた鉄筋コンクリート造の学校が次々と建てられていく。復興建築の学校の一部が平成まで使用された理由は、単に耐震・耐火構造がしっかりしていただけではない。当時の東京市建築局長が学校教育への多用なニーズを反映させ、現代の学校設備とほぼ同じものをこの時期に作り上げたからだ。理科室、図工室、唱歌(音楽)室、裁縫(家庭科)室といった特別教室をはじめ、水洗トイレやシャワー室まで。復興に関わった人たちの並々ならぬ思い、ぜひ会場の展示物から直に感じてほしい。
ライター/横山由希路






