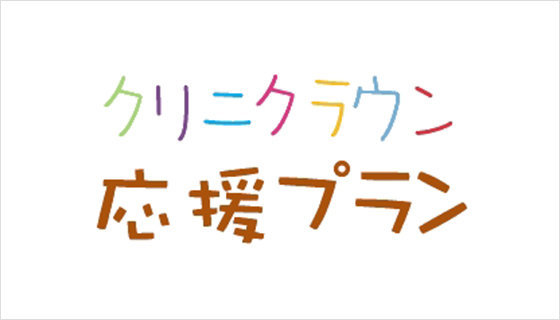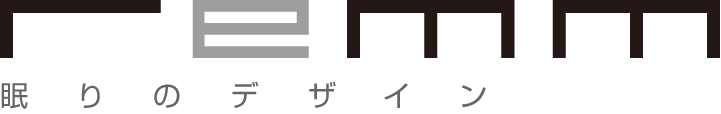
MAIL MAGAZINE Vol.2 2024
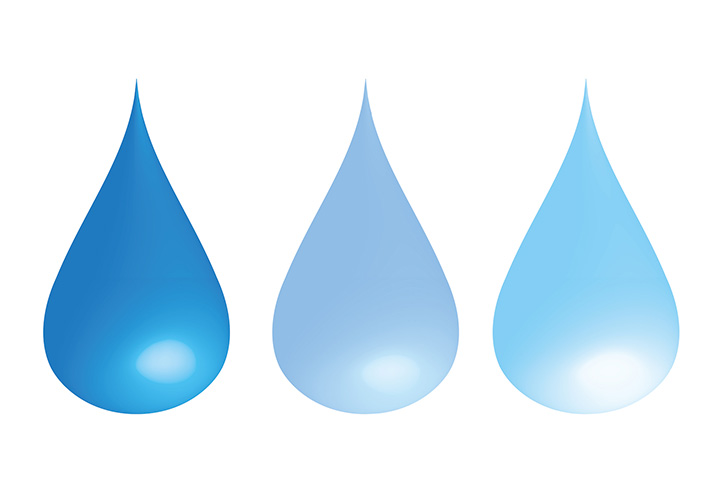
ノマドワーカーの意外な穴場!?
東京都の水道歴史館
東京・御茶ノ水には大学病院がいくつもある。私が通っていた診療科は、患者さんが日本全国から高い交通費をかけてやって来るため、通常3回分の検査や診療を同じ日に一気に行っていた。1つ終わるごとに「1時間、外に行っていいですよ」と言われ、病院の近所を散歩する。すると、年季の入った博物館に出くわす。それが東京都水道歴史館だ。
入場は無料。入口には大きな水のオブジェがある。流水音を絶えず聴いているせいか、1階ベンチでは気持ちよくてうたた寝する人も。なんだかとってものどかなのだ。
1階は「世界に誇る東京水道 近現代水道」、2階は「東京水道の起源にせまる 江戸上水」のフロアだ。1階展示の歴史は、徳川家康が江戸に幕府を開く1603年まで遡る。
100万人都市となった江戸は水不足が深刻で、同じ1600年代に玉川、亀有、青山、三田、千川と立て続けに5つの上水を開設する。人々の暮らしを支えた江戸上水も、幕府崩壊により維新後4年で所管が8回も変更。さらに木の給水管である木樋の不朽、下水の混入、コレラの蔓延などが次々と起きて、明治政府は近代水道へと急激に舵を切る。
そして「水道の危機はいつも訪れる。それは地震・台風・戦争。水がないと産業が倒れてしまう」との記述で歩を止める。元日に能登半島地震が起きたこと、断水が未だに続いていること、それによって農業、畜産業が壊滅的な打撃を受けていることを思う。また太平洋戦争中は、米軍機から東京市の水道の要である淀橋浄水場を命がけで守るため、浄水場の水瓶が田んぼに見えるように工夫を凝らしたという。
2階は、江戸時代好きな人は特に楽しめるフロアだ。実際に発掘された木樋や、町人の暮らしの中で水はどのように使われてきたのか、家屋や町などのリアルな展示も。ちなみに三田上水が開設された1664(寛文4)年の町人の水道料は、小間1間につき年間11文だったそうだ。
最後に博物館の穴場を紹介しよう。3階のライブラリーだ。絵本から専門書まで、水にまつわる書籍とデジタルアーカイブが備えてある。勉強机は4つ、テーブルの椅子は6つ。とても静かなのでパソコンは使えないが、集中する作業にはもってこい。近くに用事がある人はぜひ。
ライター/横山由希路